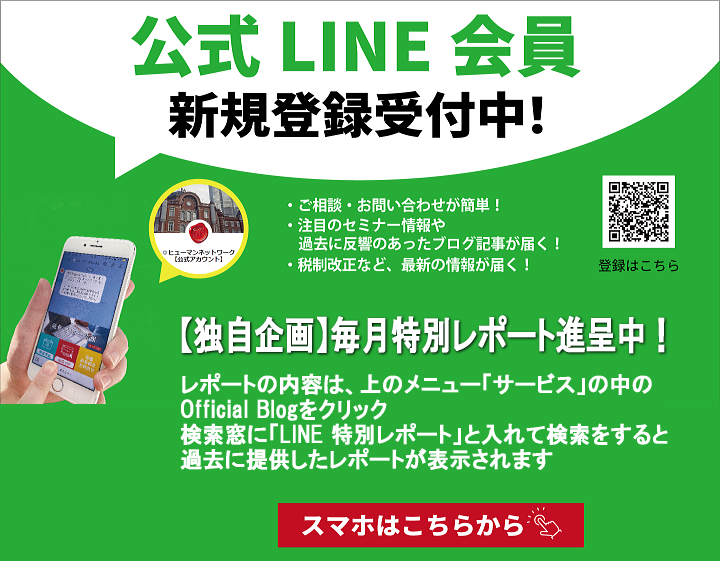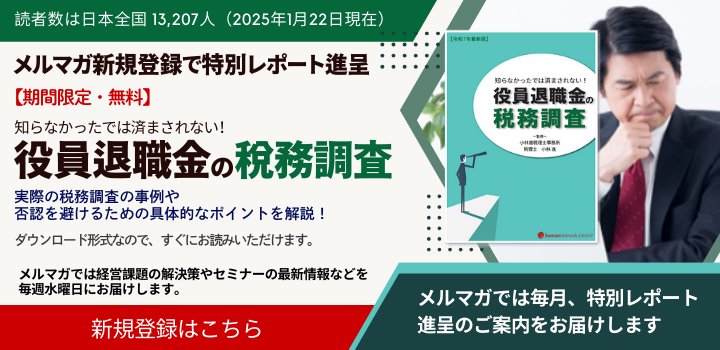雛形で決めてしまった!退職金規定で困ったこととは

退職金規定を作った際、その場では納得していても、
実際に退職金を支払う場面になると、
こんなはずではなかったと困ったことはないでしょうか。
ある会社は雛形に沿って作ったことにより、
実際に退職金を支払う場面で頭を悩ませることになりました。
今回は、その事例とどうすればスムーズに退職金を支払えたのか、
原因・解決策を交えてご紹介します。
・事例:雛形で決めてしまった退職金規定
・頭を悩ませた原因
・おわりに
事例:雛形で決めてしまった退職金規定
その会社は携帯電話販売店を経営し、
20名の社員と、社長を含む4名の役員が会社を運営しております。
株は社長が55%、他の役員は各15%保有しており、
役員退職金規程を設け、生命保険を通じて社長の死亡退職金を準備していました。
ところが、経理役員が亡くなったのです。
その役員の功績を称えて6ヶ月分の特別慰労金を出そうと考え、
社長が役員会で特別慰労金支給の承認を要求すると、
他の役員の発言により、あることが判明しました。
それは、規程によれば退職金は社長だけでなく他の役員も受け取れるということ。
規程を作った際、税理士の提案で定款に盛り込まれており、
社長はそのことを覚えていませんでした。
そのため、経理役員に支払われる特別慰労金の額は、
退職金の金額にも足りないことが判明しました。
また、今回支払うと財源が足りないため、
次の役員が辞めた場合も退職金の支払いが困難となりました。
頭を悩ませた原因
【原因1】規定を知らない
退職金規定は、税理士や保険会社からもらった「雛形」のまま
定めてしまっていることが多々あります。
また、役員退職金規程は一度定めてしまうとそれが全ての役員に適用されるため、
規程の内容とその経済的影響をきちんと理解して準備しておかないと、
急な大金の支払いが必要になります。
【原因2】財源がない
退職金制度を設ける場合、その財源を事前に計画・準備しておくことが重要です。
財源を確保していない場合、支払いが必要になった時に
会社の財政を圧迫する可能性があります。
おわりに
上記のように、役員退職金を作った際に、
税理士や保険会社の定款で決めてしまったがために、
内容を覚えていないことがあります。
社長とその家族の分だけの退職金の準備をしていれば、
問題ないと思われがちです。
しかし、時が経つと役員構成や株主構成が変わっていくことがあります。
実際に支払う場面で困らないように、
早めに役員退職金の財源を準備しておく必要があります。
弊社の「もめない診断」なら、貴社に内在する相続のリスクを発見できます。
リスクがわかることで、予め「もめごと」への対策を打つことが可能です。
ぜひ一度下記よりお試しください。
争族にならないための、もめない診断はこちら
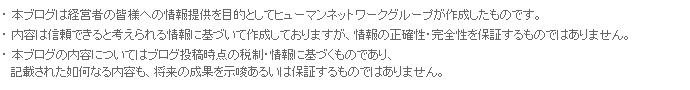
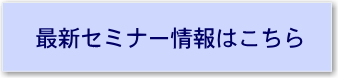 |
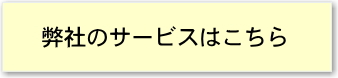 |