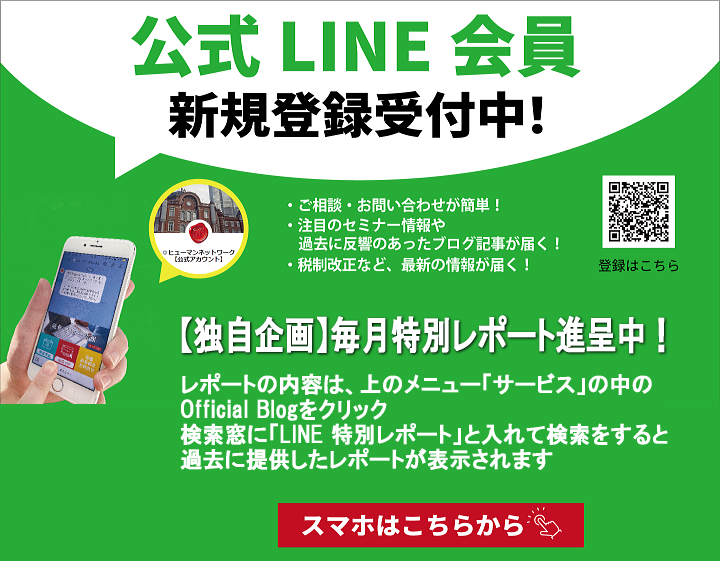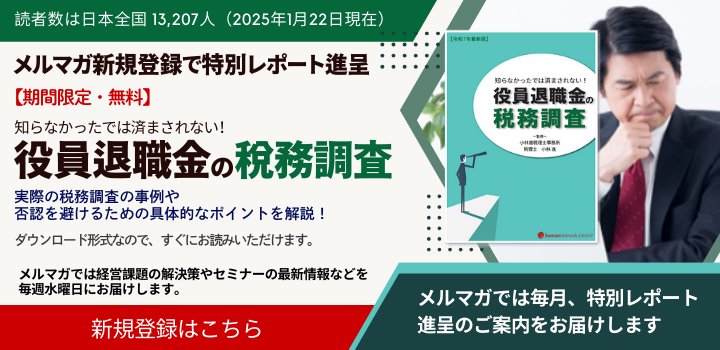断然使いやすくなった納税猶予・免除制度?!

こんにちは。東京会計パートナーズの中山です。
多くの経営者は、自社株評価額が高いため、
事業承継において、思うように自社株式を後継者に移せないというお悩みを抱えています。
そこで今回は、最近申請する中小企業が急増している、
事業承継税制(中小企業オーナーから後継者が自社株式を
贈与・相続で受けるときの税金負担を軽減する国の制度)をご紹介します。
平成27年の認定件数は、過去6年間の平均件数の2.6倍に増えています。
平成29年度税制改正大綱案でも、この制度の見直し案が発表されています。
今後年々使い勝手が良くなる予定で、さらに認定件数の増加が見込まれます。
・相続精算課税制度と納税猶予・免除制度
・おわりに
相続時精算課税制度と納税猶予・免除制度
高騰した自社株式のように高額な財産を後継者へ移動するには、
毎年の暦年贈与では期間がかかり過ぎます。
そこで一般的には、役員退職金を支払うなどして、
株価が下がったタイミングで贈与します。
自社株評価額が低くなったタイミングで、相続時精算課税制度を使うと、
その後の相続時に自社株評価額が高騰していても、
贈与時の評価額が相続税の対象となります。
ところが、贈与税の納税猶予・免除制度の認定を受けると、
発行済議決権株式数の2/3までという上限はありますが、贈与税の納税が猶予され、
その後、先代の死亡により猶予された贈与税は免除されます。
今度は、相続税の納税猶予・免除制度の認定を受けると、
贈与時の価格の80%相当額までの相続税の納税が猶予され、
最後に後継者の死亡で猶予された相続税は免除されます。
おわりに
認定を受けるには、いくつかの認定要件があります。
たとえば贈与税の納税猶予の場合、
後継者は20歳以上で贈与の日まで3年以上にわたり役員であること。
相続税の納税猶予の場合は、後継者は相続開始直前において役員であったこと。
相続開始後5ヶ月以内に代表者になること等が必要です。
またこの制度の利用には、認定を受けた後に取り消し事由に該当しないように、
きっちりフォローしていくことが重要です。
今まで国の制度は使い勝手が悪いと思っていた経営者の皆様、
この制度の上手な活用方法にご興味がある方はこちらまでお問合わせください。
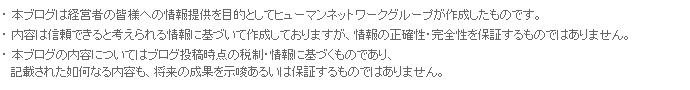
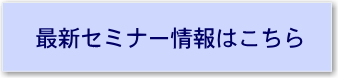 |
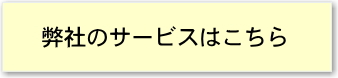 |