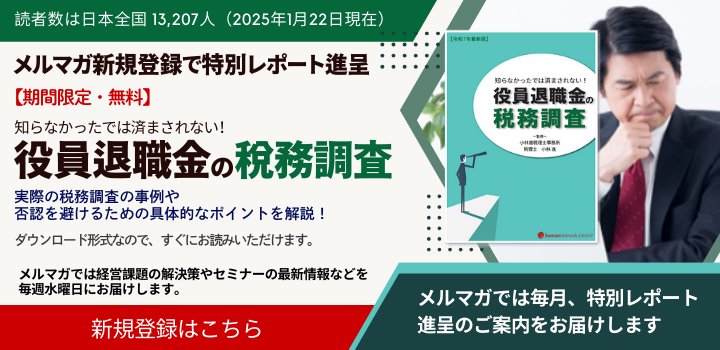まだ完了していない!?オーナー社長の自社株対策
 こんにちは経営者保険プランナーの上田です。
こんにちは経営者保険プランナーの上田です。
そろそろ4月。弊社では今年も新入社員を迎えます。
春本番。新しい気持ちで頑張りたいですね。
さて、中小企業における後継者不在が大きな問題となっている中、
親族以外を後継者として選定する親族外承継も増加しています。
4月から親族外承継でも対象となるよう遺留分特例制度も拡大しました。
事業承継に遺留分がどのように影響するのかお話し致します。
・親族外承継も対象となる遺留分特例制度とは
・遺留分特例制度によって何ができる?
・おわりに
親族外承継も対象となる遺留分特例制度とは
後継者が安定的に経営をしていくためには、
生前贈与などにより自社株や事業用資産を集中的に承継させることが必要になります。
しかし、相続人が複数いる場合、
後継者に自社株を集中して承継させても、
他の相続人から遺留分(最低限保障されている相続財産の割合)を
取り戻すための請求をうける可能性があります(遺留分減殺請求)。
このような問題を避けるため、
経営承継円滑化法では遺留分に関する民法の特例が規定されています。
これを遺留分特例制度といいます。
これまでは親族内承継に限り適用されていましたが、
親族外承継が増加している背景を受けて、
後継者が親族外の者でも対象となるよう制度が拡充され、
平成28年4月から施行される予定です。
遺留分特例制度によって何ができる?
仮に奥様と2人のお子様がいる現経営者が、
後継者へ自社株100万円、後継者の兄弟へ現金100万円を贈与していたとします。
10年後株価が高騰し、1000万の評価になった時に現経営者の相続が起きた場合、
株価は相続時の時価で評価されます。
相続財産の差を不服に思った兄弟は、
高騰した自社株評価に対して遺留分1/8を請求することができます。
後継者は1/8に見合う現金を別途用意しなくてはなりません。
そこでこのような問題を避けるため、遺留分特例制度があります。
後継者が現経営者から贈与等をされた自社株について相続人全員が合意し、
一定の手続きを行うことで遺留分算定基礎財産から除外する「除外合意」や、
価額を合意時の時価に固定する「固定合意」をすることができます。
除外合意により後継者が贈与等で取得した自社株について
他の相続人は遺留分の主張ができないため、
自社株が分散するのを防止できます。
また、固定合意では自社株の価額が高騰しても遺留分の額に影響しないため、
後継者は相続時に想定外の遺留分の主張を受けることがなくなります。
おわりに
よく、「株はほとんど後継者に贈与している。
他の子には現金贈与をしているから大丈夫」と仰る方がいます。
しかしこれでは十分な対策とは言えません。
なぜなら、株価が高騰している状態で他の相続人から遺留分を請求されてしまえば、
後継者は遺留分に見合うだけの現金を分ける必要があるからです。
しかも、相続発生後10ヶ月以内に分割協議が成立しなければ配偶者控除も使えず、
相続税が多額にかかる可能性があります。
相続によってこのような問題が起きないよう、
今のうちから後継者に現金資産を構築する必要があります。
代償分割によって後継者の方から
相続人へ遺留分に見合う現金を分けることで争続対策になります。
個人資産を上手に構築する方法にご関心がある方は、
是非弊社までお問い合わせください。
具体的な方法をご提案させていただきます。
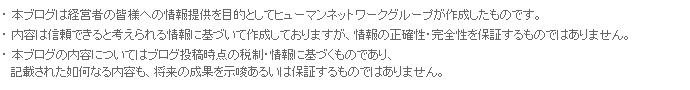
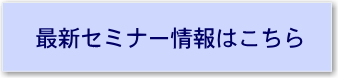 |
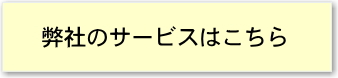 |