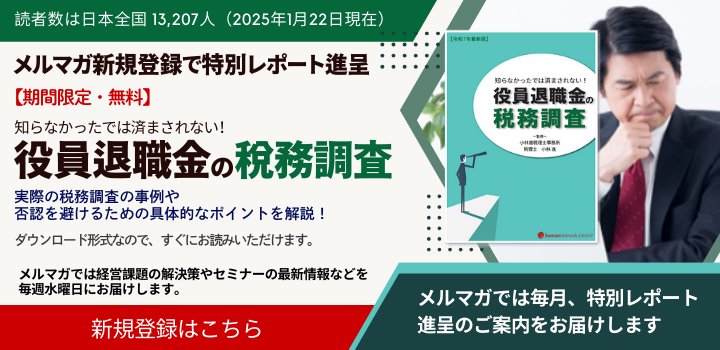方法を少し変えるだけ!!有効な決算対策とは?
 こんにちは、アシスタントの菊地です。
こんにちは、アシスタントの菊地です。
社長や役員に万一のことが起きた場合、
会社が被る有形・無形の損失は、はかりしれません。
そのため経営者保険の本来の意味は、社長・役員に見合った保障、
すなわち高額な保障をかけることです。
法人契約の保険は、その企業の中での地位や役職によって
「職務に見合った保障金額」をかけることが、大切です。
社長様は、既にご自身に見合った保障金額の保険に
加入していると思います。
そこで、未だ役員ではないが、
近い将来事業承継を予定しているご子息がいる場合、
どのように十分な保障を確保するのかについてご紹介します。
また、後継者を被保険者とした保険活用で、
効果的な決算対策方法についても触れていきます。
・次期社長の保険活用~後継者の保障と決算対策~
・チェックポイント
・おわりに
次期社長の保険活用~後継者の保障と決算対策~
法人加入での保険金額は、原則、
その職務に見合った保障金額となります。
会社の将来を担う後継者には、
高額な保障が必要です。
しかし、高額な保障を確保するにあたり、
未だ役員にもなられていない後継者が、
現在の社長様よりも多額の保障金額で加入をすることは、
保険会社から加入を認められないケースがあります。
また、税務調査で指摘をされるリスクもあります。
一方で、社長様のよりも年齢が若くて、健康な方の場合は、保険料が安くなり、
また、保険を解約したときに戻ってくる率は、高くなります。
そこで、保障の確保といった観点だけでなく、
「決算対策」として、後継者を被保険者として保険加入を検討する場合があります。
例えば、社長様や役員様のお体の状態がご病気等で悪く、
ご本人では、保険に加入が出来ないケースなどです。
そのような時に、会社で既に働いている社長様のご子息様が
未だ役員になっていない場合でも、保険契約の被保険者として、
高額な保障を確保するとともに、効果的な決算対策を行うことができます。
チェックポイント
一般的に高額な保障の保険に加入する際、
保険会社は、下記の項目をチェックします。
①被保険者のその企業での職務(役員として登記しているのか?)
②被保険者の年収
②契約者となる法人の近年の年商や設立年数
後継者が、既に役員として登記されている場合は、
年収や法人の年商等の申請で加入可能となります。
しかし、後継者が役員としての経営経験が不足していることや
現場を経験させたいとの理由で、
現時点では役員登記せずに「従業員」として働いている場合、
「高額な保障金額の保険」には加入できません。
そこで、役員登記はしていないが、「役員と同等の業務や収入がある場合」は、
保険会社へ申請することにより、役員と同額の保険加入を認められることがあります。
①いつ頃、役員登記する予定なのか
②後継者の年収
③会社の年商
等を保険会社に書面で報告をすることによって、
役員登記していない後継者でも高額な保険に加入することが可能となります。
おわりに
保険会社が1社だけだと、加入できる額も限度がありますが、
弊社が取り扱っている20社の中から条件が良いものを
数社選んで、活用することができます。
「まだ役員じゃないし・・」
「まだ従業員として経験させたいけど保険には早いうちに加入させたい・・」
など、ご要望がありましたらお問い合わせください。
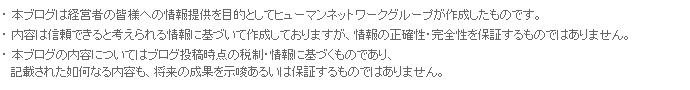
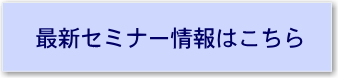 |
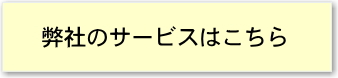 |