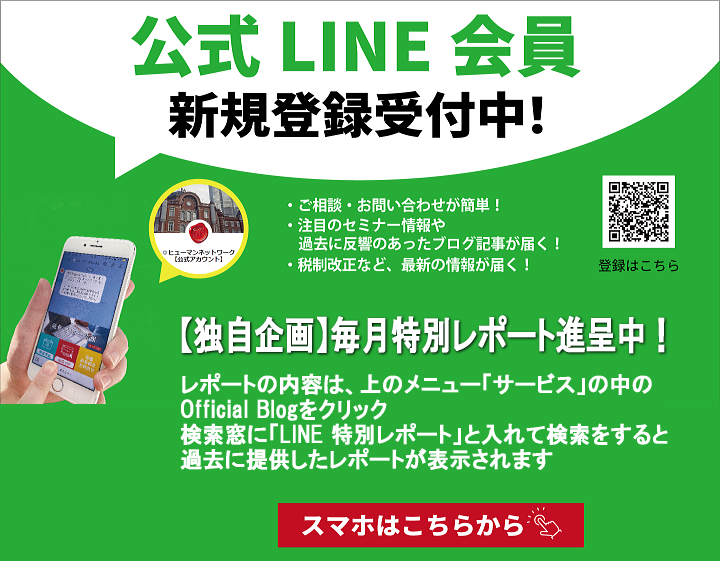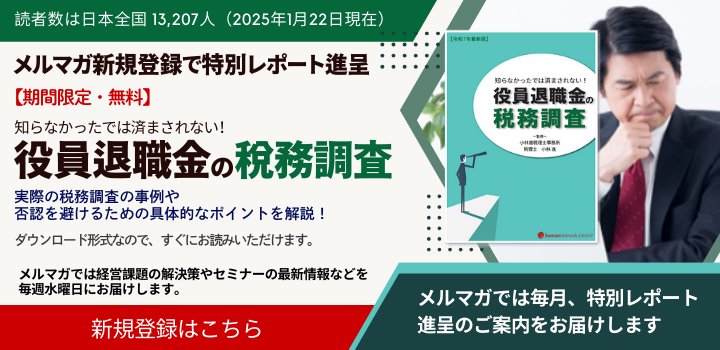「2次相続」の落とし穴?
いつもブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。
最近、目覚しより早く目が覚めてしまい、朝の出社が早くなった草薙です。
暑さで寝苦しい為か、年令のせいかは判りませんが
いずれにしても早起きは良いことなので、このまま続けるつもりです。
さて、今年から相続税の基礎控除が引下げられたことで、
相続税対策に関心を持つ人が増えているように思います。
ただ、目先の節税対策にとらわれ過ぎた結果
「2次相続」で損をすることもあるそうです。
・「2次相続」とは
・「2次相続」の損
・おわりに
☑2次相続とは
例えば、夫が先に亡くなり、その遺産を妻と子供が受け継ぐのが「1次相続」
その後、妻が亡くなり子供だけで相続することを「2次相続」といいます。
ご存知の方が多いと思いますが、
1次相続では「配偶者の税額軽減」があるため、
「法定相続分」または「1億6千万円以下」のどちらか多い方までなら相続税はかかりません。
従って、出来るだけ多く配偶者に遺すことが得するように見えます。
しかし先日、税額軽減を使って配偶者に多く遺こしたために、
結局、「2次相続」で損をするという相続税の計算式が新聞で紹介されていました。
☑2次相続の損
例えば、1億8千万円の遺産のうち、
妻が1億6千万円、一人の子供が2千万円を相続した場合です。
「1次相続」では、妻の相続税はゼロ、子供は304万円ですが、
そのあと「2次相続」で、妻の1億6千万円を子供が相続すると、
3,260万円も相続税が掛かります。
1次、2次、トータルで3,564万円です。
これに対して、「1次相続」で最初から妻と子供9千万円ずつ相続した場合、
子供が払う税額は、1,370万円となりますが、
そのあとの「2次相続」では920万円に抑えられます。
結果として、トータル2,290万円です。
「配偶者の税額軽減」を優先した場合に比べ、1,270万円の節税です。
相続対策は「2次相続」まで見据えることが必要であり、
目先の対策だけを考えては結果的に損をする、という事例です。
☑おわりに
そんな先まで見据えた対策は、現実的に難しいのかも知れませんが、
相続争いの多くは「2次相続」で起きています。
配偶者軽減が使えない重税感と、仲裁役となる親が居ないことが原因のようです。
そう考えると、優先すべきは相続税対策ではなく、
生前から、ご家族にご自分の想いや考えを伝えて置くこと、
そういった話合いの場を持つことが、大切なのかも知れません。
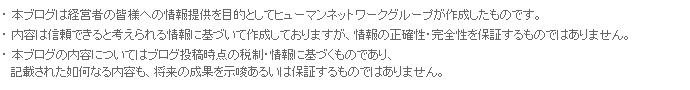
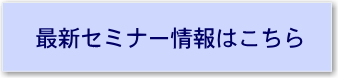 |
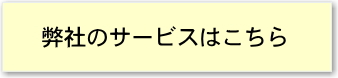 |