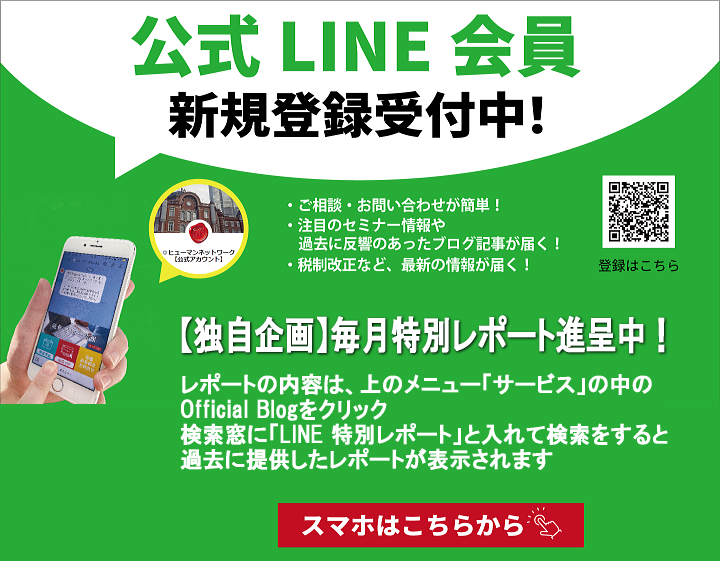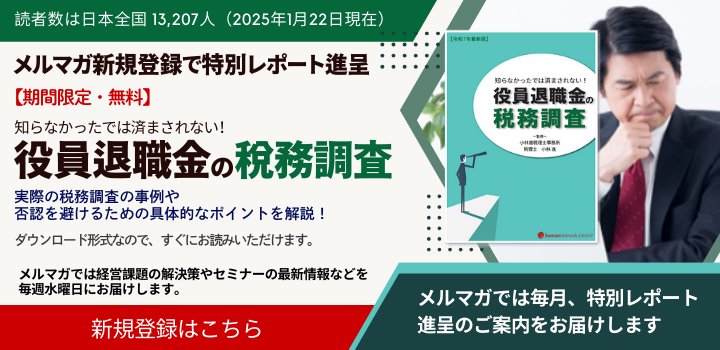相続税の納税猶予制度の注意点
こんにちは!経営者保険プランナー、相続診断士の加藤です。
5月半ばというのに、東京では連日30度近くの気温が続いています。
普段外に出ることの多い私にとっては、これからが戦いの季節!
水分補給と熱い気持ちで乗り越えていきたいと思います。
今年の夏も応援よろしくお願いいたします。(笑)
さて、経営者様のところにお伺いする中で、納税猶予制度について
ご質問を受ける機会が多くあります。
そこで本日のブログでは、相続税の納税猶予制度のポイントと注意点についてお伝えします。
☑相続税の納税猶予制度のポイント
納税猶予制度には、贈与税の納税猶予制度と相続税の納税猶予制度の2つがあります。
今回は、相続税の納税猶予制度についてお話しします。
相続税の納税猶予制度とは、後継者が相続した同族株式(発行済株式の2/3まで)に
かかる相続税額のうち80%が猶予される制度です。
個人財産に占める自社株の割合が大きいオーナー経営者にとっては魅力的な内容で、
突然相続が発生した場合に頼りになる制度といえます。
一方、ひとたび適用を受けても、その後継続して猶予を受けるためには
いくつかの要件があります。
☑相続税の納税猶予制度の注意点
猶予の適用から5年間維持しなければいけない要件には
次のようなものがあります。
①後継者が会社の代表者であること
②雇用を5年間平均で8割以上維持していること
③後継者が筆頭株主であること
④上場会社、風俗営業会社に該当しないこと
⑤猶予対象株式を継続保有していること
⑥資産管理会社に該当しないこと etc・・・
5年経過した後も、継続要件があり、それらを維持できなくなった時点で
納税猶額と猶予期間に対する利子税を併せて納付しなければならないという
厳しいルールが存在します。
また、猶予の要件の中に「猶予株式の継続保有」が含まれることにも注意が必要です。
これは、納税猶予の適用を受けた株を「譲渡」してはいけないというものです。
株を譲渡した時点で納税猶予は終了し、税金を支払わなければいけないことになります。
このような制約は、制度を利用し続ける限り続くため、
将来的に後継者から次の後継者へ株を移転するときの障害となる恐れもあります。
制度の採用にあたっては、以上のような点もふまえた十分な検討が必要であるといえます。
☑おわりに
相続税の納税猶予制度は、一度はじめたら終わりがありません。
また、現在の経営課題を解決できたとしても、
会社の将来にさまざまな制約を残すことが考えられます。
制度の特徴やメリット・デメリットをよく理解した上で、
慎重にご判断いただくことをおすすめいたします。
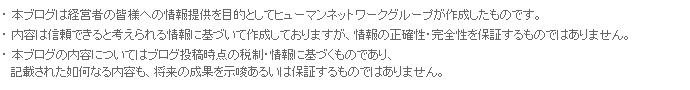
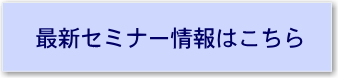 |
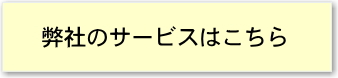 |