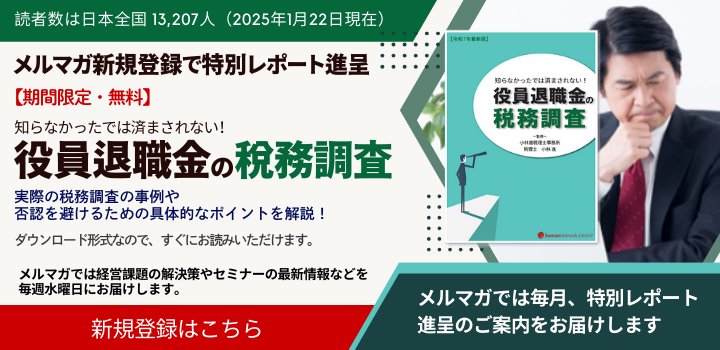効率的な役員退職金の準備方法とは?
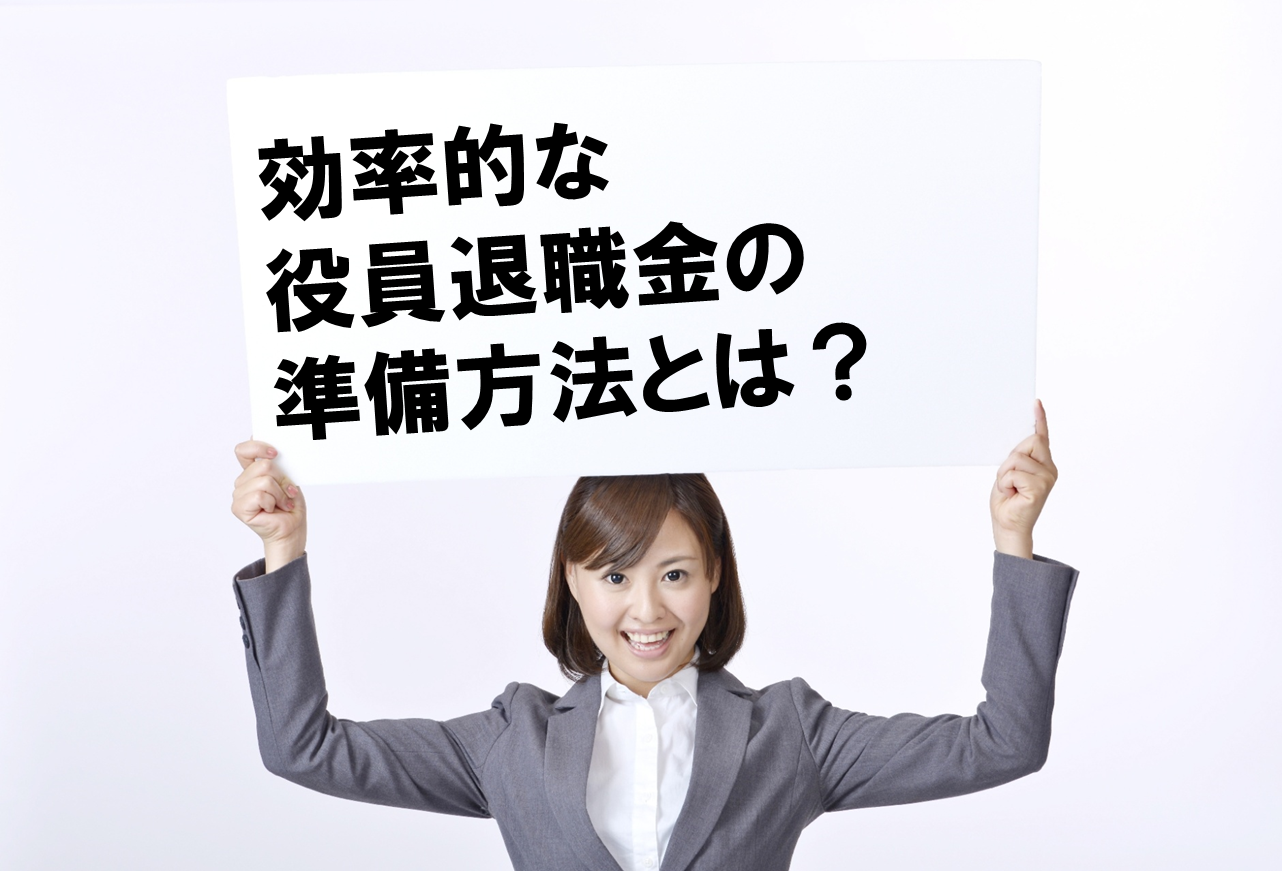
こんにちは!経営者保険プランナー、
相続診断士の肥後です。
寒くなり風邪を引きやすい季節がやってきました。
私はとりあえず出来ることとして、
「イソジンでのうがい」を毎日しています。
効果のほどは賛否両論あるようですが、
とりあえず「風邪を引かない」という
暗示にはなると思い続けています。(笑)
さて今回は、前回に引き続き「役員退職金」がテーマです。
前回のブログでは、役員退職金の分割支給が否認された事例を紹介し、
できれば退職慰労金を一括支給できるように
会社の資金を事前に準備しておくことをおすすめしました。
今回はこの資金準備の方法についてお話したいと思います。
・退職金準備4つの方法
・会社の現金から支給する
・金融機関から借りる
・有価証券や不動産を譲渡する
・生命保険を活用する
・おわりに
✔退職金準備4つの方法
一般的に役員退職金の資金準備の方法は次の4つがあげられます。
1.会社の現金から支給する
2.金融機関から借りる
3.有価証券や不動産を譲渡する
4.生命保険を活用する
✔会社の現金から支給する
「会社の現金から支給する」ためには
当然ながら税引後の利益を貯めていくことになります。
まだまだ日本の法人税は高いですし、
会計上の利益=現金残高ではないことからも貯めていくのは大変です。
また貯まったとしてもお金に色がついているわけではないので、
日々の運転資金や設備資金等に使われ、
「役員退職金」として残せるかは確実とはいえません。
また仮に会社に現金が潤沢にあったとしても、
高額な役員退職金は支給時の決算期に一度に特別損失として計上されますので、
赤字、さらに債務超過になる危険性もあります。
✔金融機関から借りる
2つ目の方法として、現金がない場合は、
「金融機関から借りる」ことになるわけですが、
後継者のその後の負担を考えますとできれば避けたいところです。
✔有価証券や不動産を譲渡する
また3つ目として、会社に「有価証券や不動産」があり、
これらの資産を退職される社長に
現物支給するといった方法をとられるケースもあるようです。
このケースでは価格の変動が大きいため、
計画通りの金額にならなかったり、
またこうした資産を個人で持ち続けますと
将来の相続税納税・財産の分割が難しくなるリスクを考える必要があります。
これらを考えますと、できれば現金で支給を受けたいところです。
✔生命保険を活用する
4つ目の「生命保険」を多くの企業様が活用されるのは、
損金性のある商品を選択することで税引前の利益をストックでき、
退職金支給時の赤字、さらなる債務超過を防ぐことができ、
確実に現金が簿外に(別立てで)貯まっていくという利点があるからです。
ただし、商品によって損金割合も、
貯まる割合(返戻率)もかなり違いがありますので
幅広い選択肢のなかから検討することをおすすめいたします。
✔おわりに
今回は、一般的な役員退職金の資金準備の方法についてお話してきました。
会社の状況によっても効果的な対策は変わってきますので、
自社にあった方法を十分検討し、選択されることをおすすめいたします。
次回以降はテーマを変えまして
「日本の法人税は本当に高いのか?」について
お話ししていきたいと思います。
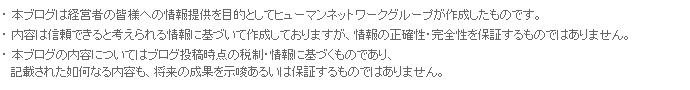
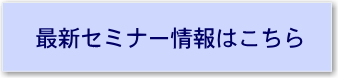 |
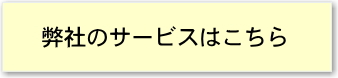 |